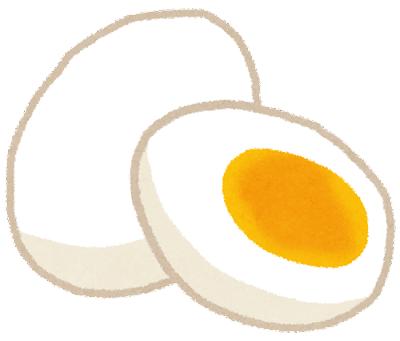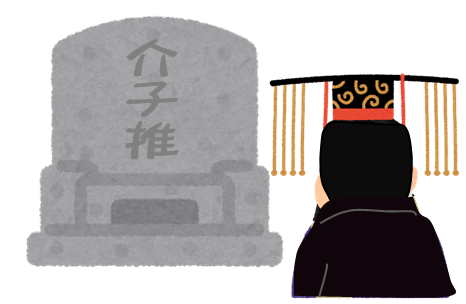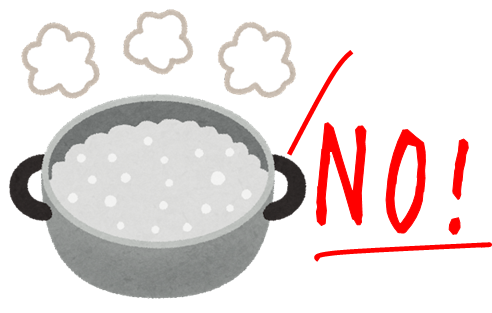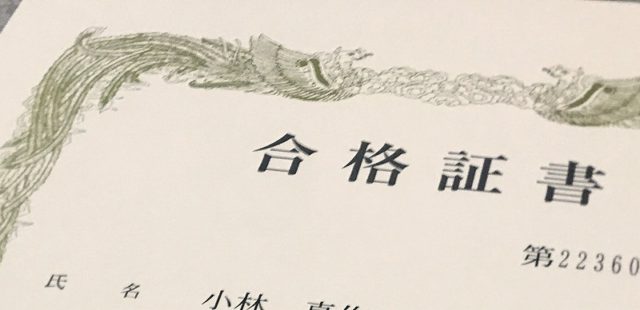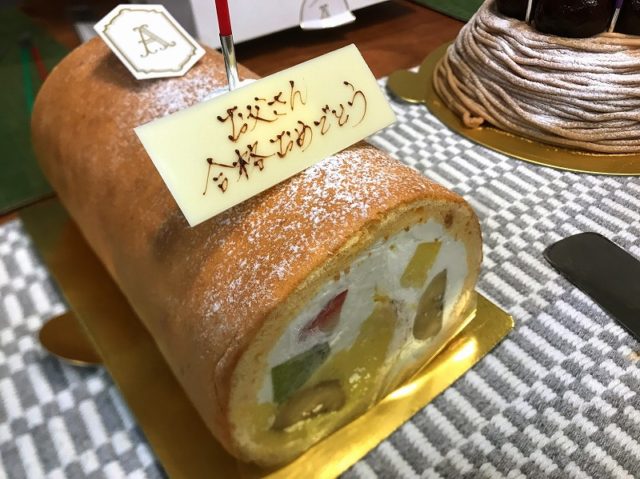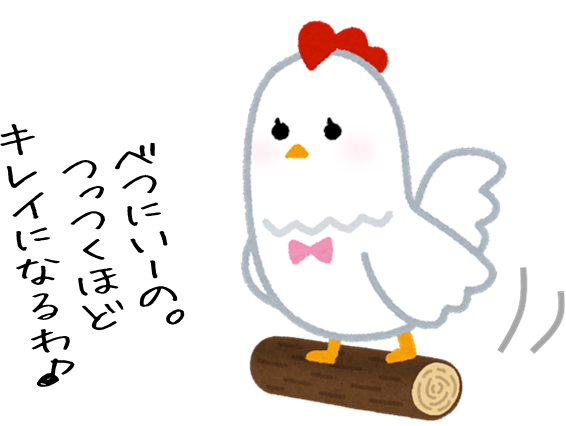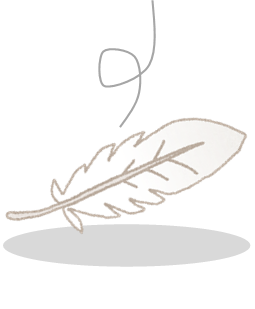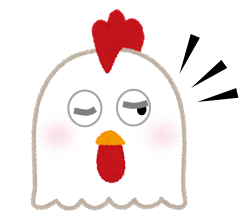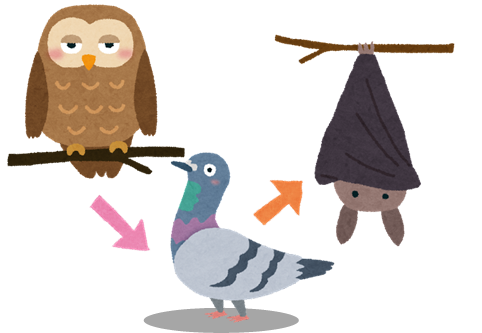こんにちは!
たまごのソムリエ・こばやしです。
先日ニューヨークさんの番組に
出させてもらったのですが、
その時のクイズのひとつが
「王子の狐」という落語で、
玉子焼きが出てくるお話でした。
僕は大の落語好きなのですが、
もうひとつ、たまごの出てくる
落語の演目があります。
「夢たまご」というお話です。
故桂枝雀さんのお話で、
名演がCDに残っています。
どんなお話かというと・・・
長屋で寝そべっていた男
ちょっと小腹がすいたな・・
と思っていたところ、外から
物売りの掛け声が聞こえてきた。

「たまご〜、たまご〜、
夢たまごぉ~、1つ1銭ン〜。」
おお!ゆでたまご売りか、
と呼び止めてみると、
『ゆでたまご』じゃなくって
『ゆめたまご』だという。
見てみると
赤卵や白卵、いろんなのが
かごに入っていて、
なんでも食べると必ず
「夢をみる」んだそう。
こりゃ面白い、ってんで
一つ買って早速食べてみる。
すると、
「たまご〜、たまご〜、
夢たまごぉ~、1つ1銭ン〜。」
と自分が卵を売っている夢、
つまり『夢たまご売り』に
なった夢をみている・・・。
夢の中で夕刻になって
売り終わり家に帰ると、
夢たまご売りの?
息子がいる。
嫁さんがいる。
夢の中だと
自分の嫁さんだしな~・・・
ってんで布団に入ってから
手を出そうとしたところ、
夢たまご売りが現れて
「ヒトの嫁さんに何するんじゃ!」
とボコスカ殴られてしまう・・・
というところで男は目を覚ました。
ああ、やっぱり夢だったんだ。
しかしあの夢たまご売りは、
俺が夢ン中で嫁さんにちょっかい
出したことなんてちっとも
知らないんだもんなぁ。
おもしろいわ~。
そう思っていると、
夢たまご売りの掛け声が
外から聞こえてきて、
「たまご〜、夢たまご〜、
なんぼ夢の中でも〜
してええことと
悪いことがあるぞ〜!」
というお話です。
幻想的というか、
ちょっとSFチックで
ドラえもんの『うつつマクラ』
みたいなお話で
非常におもしろいです。

この噺、
実際に聴くと
めっちゃ美味しそうに
カラを剥いて食べる様子
なんかもあって、
たまご屋としても
大満足なんです。
◆ゆでたまごは安眠効果がホントにある
じっさい、
たまごの成分には
安眠効果があります。

たとえば、睡眠をおこす
メラトニンになる素材の
トリプトファンが、
たまごにはたっぷり含まれています。
また、同じく豊富なビタミンDも
最近の研究では安眠に効果ありと
言われています。
そして、
逆に目覚めた後の
活動時に食べると、
卵白ペプチドが
スッキリ目覚めを
手助けしてくれるという
寝るに良し
起きるに良し
の生活に質を上げるのが
卵のメリットなんです。
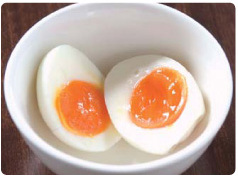
ぜひ卵を食べて、
質の高い睡眠で、
夢たまご的な
たのしい体験を
すごしてくださいませ~。
ここまでお読みくださって、
ありがとうございます。