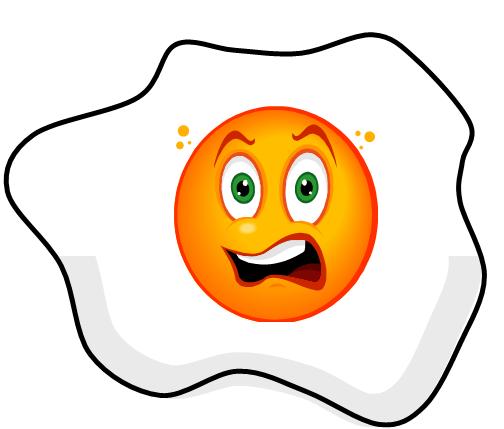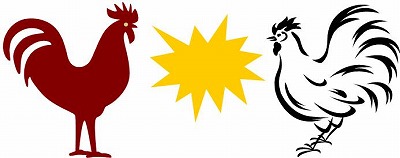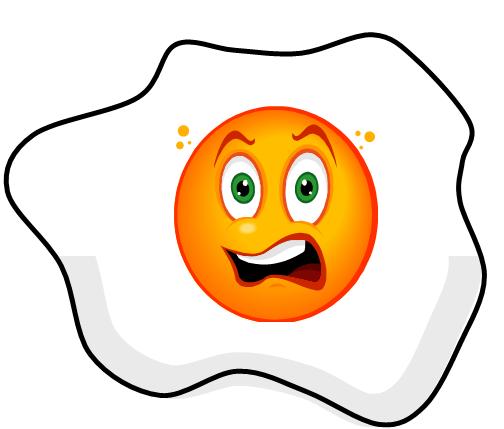
こんにちは!
たまごのソムリエ・こばやしです。
暑い日が続きますねー。
息子と半日泳いでいたら、
上半身まっ赤っ赤になってしまいました(^^;)
さて、本日はひんやりする話を。
日本でたまごが
日常的に食べられるように
なったのは、江戸時代から。
それまでは一般的に、
卵をたくさん食べるのは
「ちょっと恐ろしいコト」
だと考えられていたんです。
こんなお話しが残っています。
『日本現報善悪霊異記』(822年)
因果応報を信じないある男が、
毎日鳥の卵を探し出しては、
煮て食べていた。
ある日、
男の前に異形の兵士が現れた。
「国府からの命令ダ。ツイテコイ。」
男は兵士の後をついていくと、
兵士は突然、
眼前の麦畑に男を押し込んだ。
と、
二尺の高さに生い茂っていた麦が
燃えあがる火と化した。
足の踏み場もない!
燃え盛る炎の中を、
「熱い熱い!」
と泣き叫びながら
男は逃げ惑うが、
どこにも出口がない・・・!
さて、近隣の村人が
麦畑の近くを通ると、
「熱い熱い!」と叫びながら
麦畑を走り回っている男がいる・・・。
不届きなイタズラ者め!
と男を捕らえようとするが、
泣き叫ぶばかりで暴れるのを止めない。
ようやく捕まえて、
強引に畑から引きずり出した
ところ、
倒れ伏してようやく動かなくなった。
男は痛い痛いと呻きながら
「火の山の中を走り回っていたんだ!」
とこれまでのことを説明した。
村人達が驚き
裾をめくって足を見ると、
男のふくらはぎの肉は焼け爛れ、
骨だけになっていた。
そのまま翌日に
死んでしまったという。
この世にも地獄というものが
あるんだなぁ、と
村人たちは話し合ったそうである。
編者曰く、
「現世で鳥の卵を
煮たり焼いたりする者は、
死んでから 灰河地獄に落ち、
煮られた卵と同じ目に合うのである。」
・・・・・・と、
因果応報の大事さと
殺生を禁じる言葉で締めくくった。
と、いうお話です。
うーむ、
たまごを煮ちゃいけませんか・・・。
僕はたまご屋さんなので、
毎日ゆで玉子やオムレツ、
目玉焼きを食べてるんですよねェ。(^^;)
この書が編纂されたのは平安初期、
作中の時代は奈良時代です。
お坊さんが
仏教の教えを広めるために、
わかりやすいエピソードを
まとめたもの、と言われています。
仏教では「無傷害」という言葉があり、
生命のあるものを傷つけること
「殺生」を禁じています。
ですので、
この『日本霊異記』にある
エピソードでも、
猟師さん、漁師さんなど
狩りをする者はかっこうの
「ワルモノ」扱いです。
ただ、
現代に至る仏教の解釈では、
殺生がいけないわけじゃなくて
単に「快楽のためだけに殺生をすること」
がいけないことである、
という考えにも至っています。
不殺生を突き詰めると、
植物ですら生命を持ってるわけ
ですから、
何にも食べられなく
なっちゃうわけです。
そもそも、
快楽主義と禁欲主義の間の
「中道」を行くべし、
というのがブッダの教え。
現代に生きる我々としては、
「肉も魚も卵もおいしく食べるけど、
命の恵みと大切さに感謝して
無駄にすることなくいただく」
ことが地獄の炎に焼かれない
真っ当な生き方じゃないでしょうか。
・・・・・・ですよね!?(^^;)
ここまでお読みくださって、
ありがとうございます。
 こんにちは!たまごのソムリエ・小林ゴールドエッグのこばやしです。
こんにちは!たまごのソムリエ・小林ゴールドエッグのこばやしです。