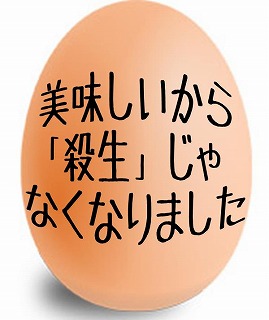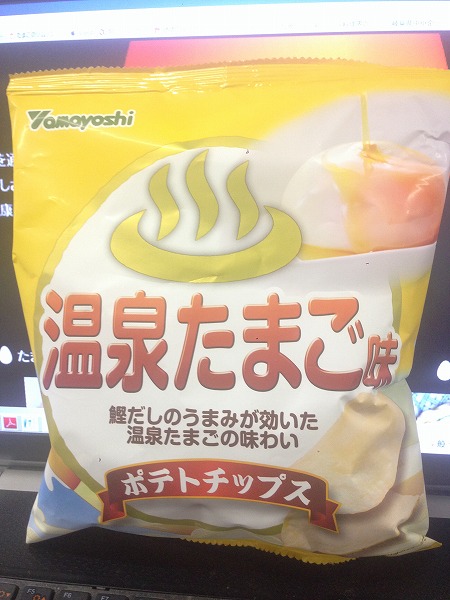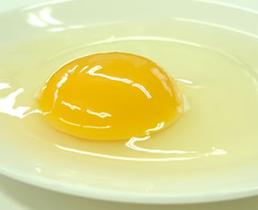こんにちは!たまごのソムリエ、小林ゴールドエッグのこばやしです。
たまごが出てくる映画の名シーンご紹介、第6弾です。今回は「ミスターロンリー」。2007年作の英・仏・米合作映画です。

舞台はパリ。主人公“マイケル”は生活のすべてをマイケルジャクソンになりきって生きるモノマネ大道芸人。 ある日、マリリンモンローのソックリ芸人“マリリン”と出会い、彼女に惹かれていきます。そして『誰かになりきることでしか生きられない芸人』たちの理想郷・コミュニティに足を踏み入れることに……。
チャップリンにジェームス・ディーン、リンカーン大統領など、アノ有名人たち(偽者ですが)が集まって大騒ぎする様子はかなりシュールで面白く、そして幻想的でもあります。有名人を模すことで生きる彼らの楽しみや悲哀と葛藤、そして恋心にしみじみする映画です。
◆たまごに重なる歌が思わずジーンとくる名シーン!
物語後半に主人公マイケルが、みんなの似顔絵を描いた卵を一人部屋で見つめ、その卵達が歌いだすシーンがあるんです。この切ない歌がまた良いんですよねー!Iris DeMentさんの“ My Life”という歌です。
映画好きとしてもたまご屋としても、すごく印象に残るシーンでした。
映画自体は、全く絡まない2つのストーリーが平行していたり、ちょっと難解な内容ですが、“映像”として非常に楽しく印象的な映画です。 ぜひ機会があればごらんくださいませ。
ここまでお読みくださって、ありがとうございます。