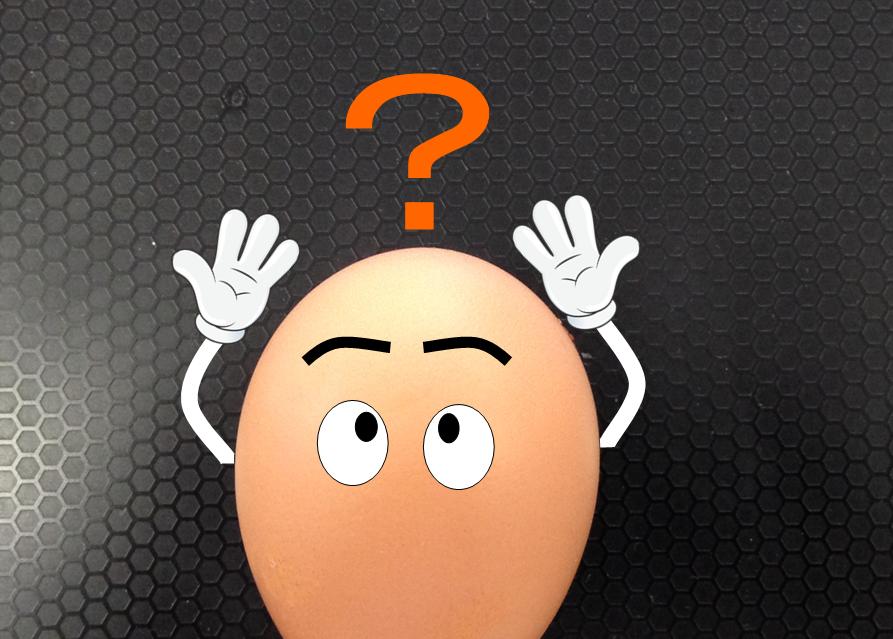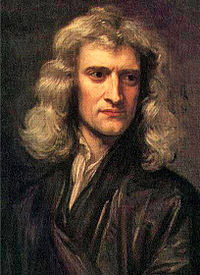こんにちは!たまごのソムリエ・こばやしです。
涼しくなって、スイーツの美味しい時期となってきましたね!
スイーツと卵は切っても切り離せない関係ですが、特に卵が重要なのが、たっぷりの卵をつかう「シュークリーム」。
16世紀中ごろに、イタリアより伝わったのが起源とされています。
その際は、ふっわふわの膨らんだシュー外側を作るために、ふんわりパリッと揚げてしまうのが普通のやり方だったそうです。

作り方の一部を引用すると
『(前半略) 卵は生地が充分に柔らかくなるまで入れる。 次に、良く煮溶かしたバターを火にかけ熱する。 生地を銀の匙でウズラほどの大きさにすくい、一度に18-20個ずつバターの中に入れ、網杓子で頻繁にかえしながら、生地にひびが入るまで揚げて、取り出す。(以降略)』(ランスロ・ド・カストー著「料理入門」1604年)
・・・・・・というようなレシピでした。(ちなみに生地もクリームにも、たーっぷりの卵を使用します!)
たっぷりの溶かしたバターで揚げる・・・・・・
空前のバター不足に苦しむ今年の日本からみると、めちゃくちゃ贅沢な気がしますねー^^;
この「揚げシュークリーム」という手法は現代にもしっかりと残っておりまして、なんといっても大きなメリットは、オーブンなどが無くてもできること。 ご家庭で美味しく作られている方も沢山いらっしゃるようです。これは、カレーパンなんかも同じですね。
ここまでお読みくださって、ありがとうございます。