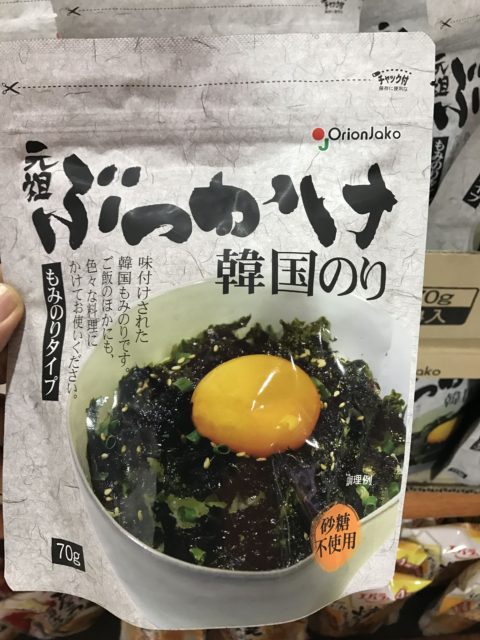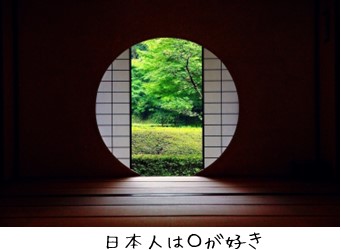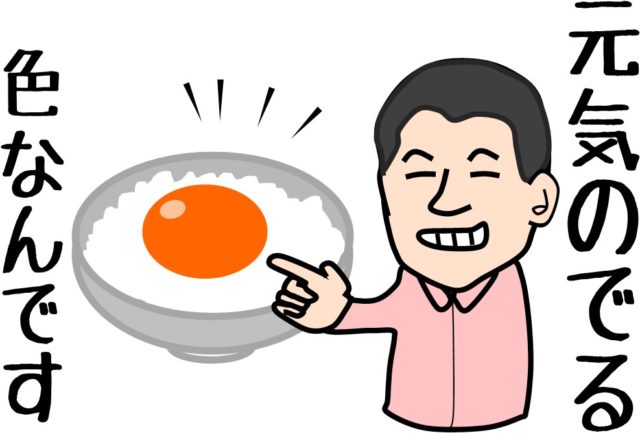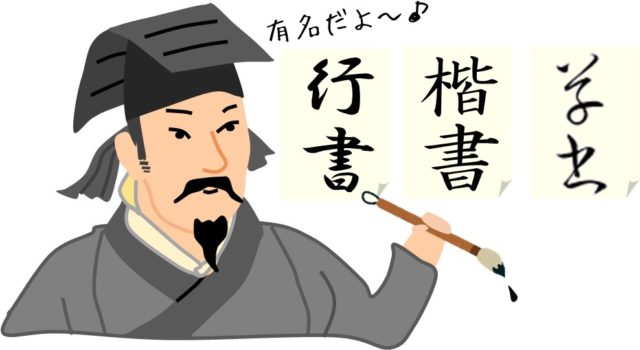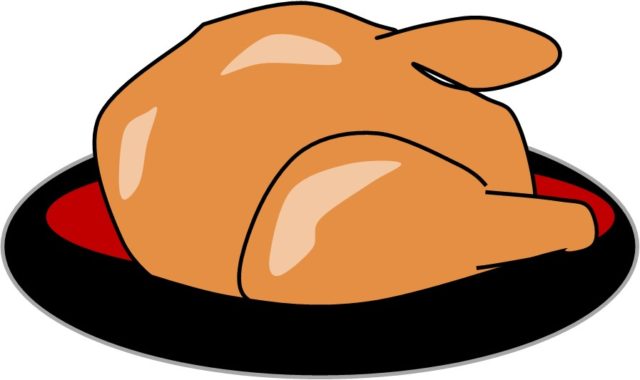こんにちは!たまごのソムリエ・こばやしです。
この美味しそうなたまごの絵が入った商品、いったい何だと思いますか?
コレ実は、ホームセンターで売っている炊飯器の外箱なんです。
良く売れているんだそうです。
以前少し書きましたが、卵の黄身を見せることで、人は目を惹きつけられます。
店舗での写真を載せたメニューイングには、積極的に黄身のシズルを取り入れるべきです。
〇日本人は世界トップクラスの卵好き
意外と意識されていない
「卵の魅力」が
黄身の「色」と「形」です。
あの黄色、あの丸みを見るとどうしても目が行ってしまうんですね。
世界トップ3に入る卵消費国の日本。
食文化的にも生卵としての黄身を見慣れていてよく食べますので、「見た目」の誘因効果としても機能しやすいんですね。
例えば下の商品メニュー。

もし黄身が無ければ、絵的にとっても地味な商品になりますよね。
こちら↓の2商品なんて『肉炒めの素』『のり』ですからたまごは入ってませんし関係無いですよね。なのに、たまごが主役級に目立っている……。

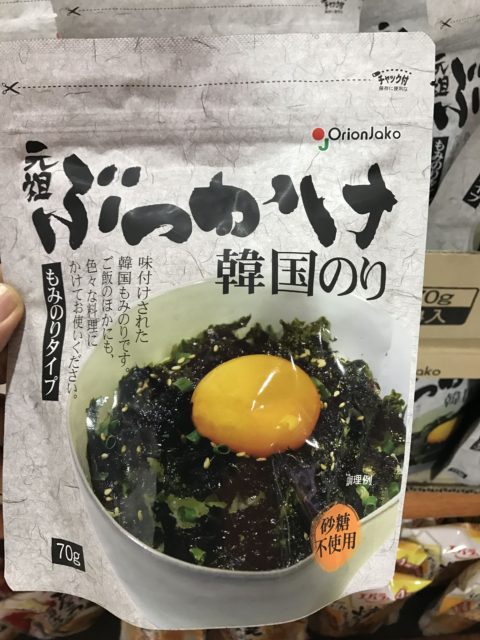
こんな風に、街中でよく見るとあちこちに「黄身」で目を惹きつける商品やメニューがあります。
冒頭の紹介のように、電化製品まで「黄身のシズル効果」を使うようになってきていますが、
それだけ「効果的」だということです。
じゃあ、なんで黄身が効果的なのかといいますと、2つ理由があります。
〇丸い形状に惹かれる
人は心理学的に丸いものに惹かれます。
人間の攻撃欲求は丸いモノを見ると弱まるのだそうで、子供のキャラクターなんかも全て丸っこくなっていますよね?
特に日本人は丸いカタチが好きな傾向があるそうで、
和菓子・茶道の影響や日本国旗など様々な様式で「〇」形が取り入れられていて、自然と丸い形状に触れていることも大きいんじゃないか、ともいわれています。
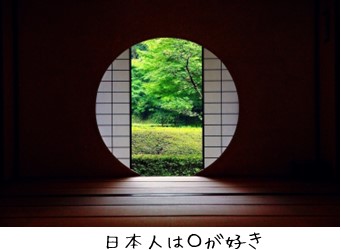
〇たまごの色味にヒトは惹かれる
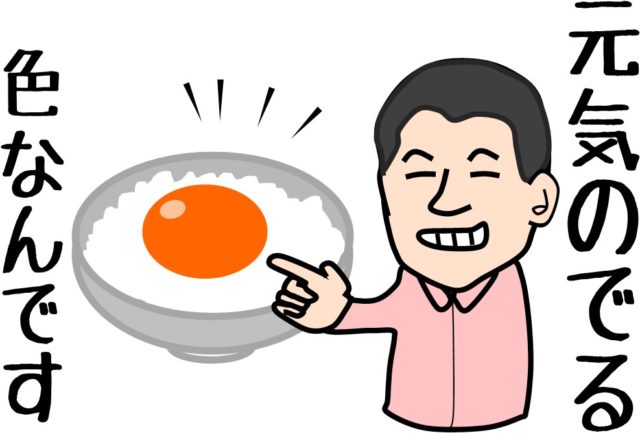
また、黄身の明るいオレンジ色は心理学的に「開放感」を掻き立てます。
ビタミンカラーとも言われるこの色味は、元気さの象徴でもあります。
○の形状とオレンジ色
この両方を併せ持つ黄身は、シズルとして人の目を引くベスト食材なんですね!
実際僕達のお客様でも、和風パスタに黄身を乗せ写真をメニューで見せたところ、
100円UPしたにもかかわらず出数は2割もアップしました。
お客様の目を引く、
粗利のとれるメニューシズルにぜひ「黄身の写真」を活用してみてはいかがでしょうか!?

ここまでお読みくださって、ありがとうございます。