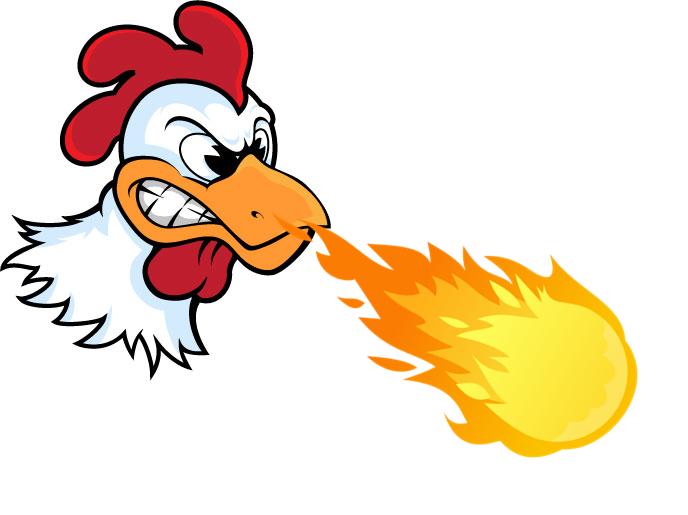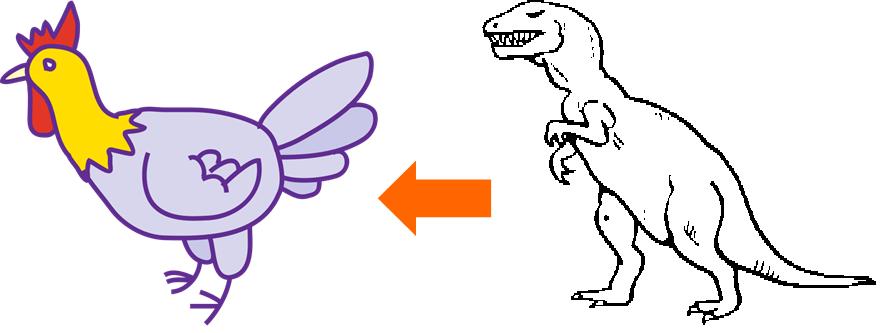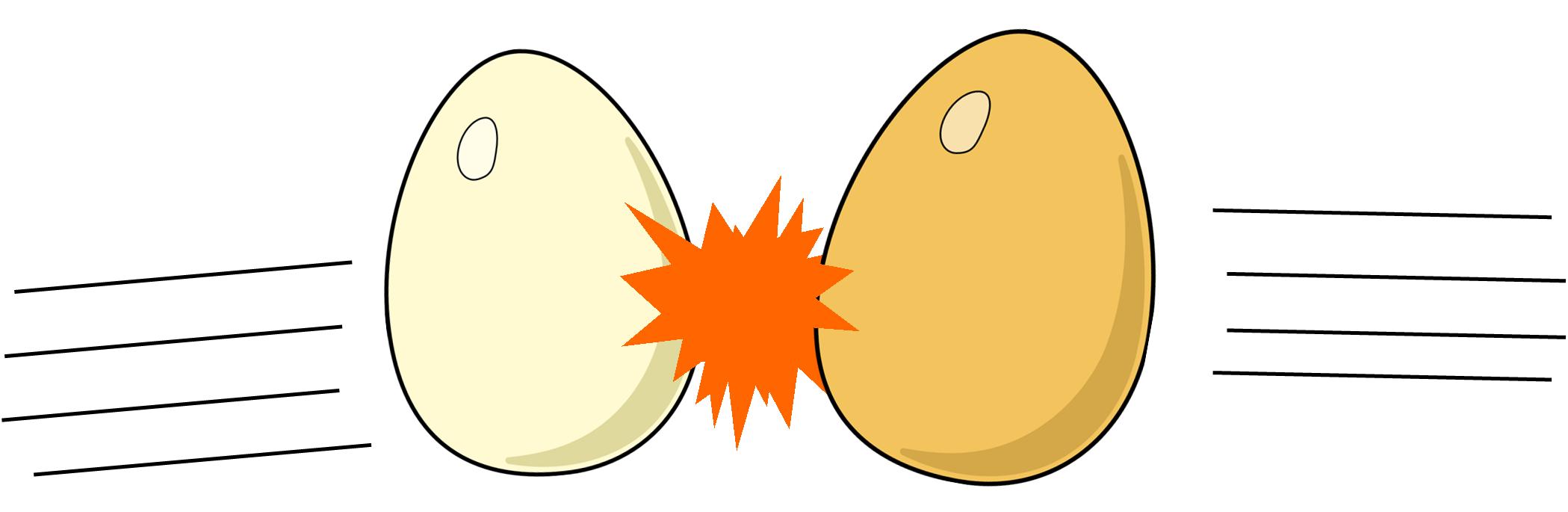こんにちは!たまごのソムリエ・こばやしです。
鍋に焼き芋、ダイエットの敵、美味料理の多い時期でもありますよねー^^
さて、山盛りのたまごを目の前に置かれ、「卵を食べつくせ!」と責められる、そしてそれをガマンする。
そんな儀式を毎年行っている神社があります。
埼玉県にある鷲宮神社と言いまして、
最近は「らき☆すた」という人気アニメに登場し、若い人のあいだでも良く知られた神社となっているようです。
この儀式は「強卵式(ごうらんしき)」と言います。
“強卵頂戴人”なるお祓いを受けた人達が、神様の使いである天狗から、まずお酒を「飲め!」と責められます。
一滴残らず全部飲み干すまで、許してくれません。
なんだか体育会系の先輩みたいですねェ。
なんとか飲み干すと、今度は大皿に山盛りのたまごが出てきます。
「この卵を食べつくせ!」と天狗にまたまた責められるのですが、今度は「食べません。この卵は、神様にお供え申し上げます。」と断わらなくちゃいけないんです。
えー・・・!?
「何を言う。食べろ!食べつくせ!」と何度も天狗に責められますが、ゼッタイに食べちゃいけません。 パワハラ先輩にはNO!という勇気です。(ちがうか)
そんな姿を見て、天狗は「立派な心がけじゃ。」としてその事を神様にご報告申し上げる・・・・・・。
・・・・・・という筋書きの神事です。
酒は飲んでもタバコは吸うな。
・・・・・・じゃなかった、タマゴは食べるな。
というわけです。
◆なぜ卵はことわるの・・・・・・!?◆
なぜ卵なのかというと、この鷲宮神社は「お酉さま」とも呼ばれ、すなわち鳥に関係があるわけです。 かつて源頼家公が病気を患ったさいに、母である北条政子が鶏肉と卵を断って祈願をしたところたちまち回復したとの故事もあり、この鷲宮神社にお参りをする際は『卵を断つ』ことが正式な祈願の方法なんだとか。
また、古来より卵は「生命の源」、神性を表わす象徴でもあります。 そのあたりのイメージも影響しているのではないでしょうか。
◆各地にある卵の「神社エピソード」◆
卵に絡んだ神社のエピソードはちらほらありまして、卵食を禁じる島根県の“美保神社”や滋賀県の田村神社、逆にお供えを奨励する群馬県“電電神社”や埼玉県出雲祝神社ちかくの“ハヤタの稲荷”などがあります。
ちなみに鷲宮神社の御祭神『天日鷲命』さまは、我が四国徳島県の忌部(いんべ)氏の祖先だそうで、なんというかご縁と親しみを感じております。
ここまでお読みくださって、ありがとうございます。
(関連:えびす様はニワトリ嫌い? – たまごのソムリエ面白コラムエ)