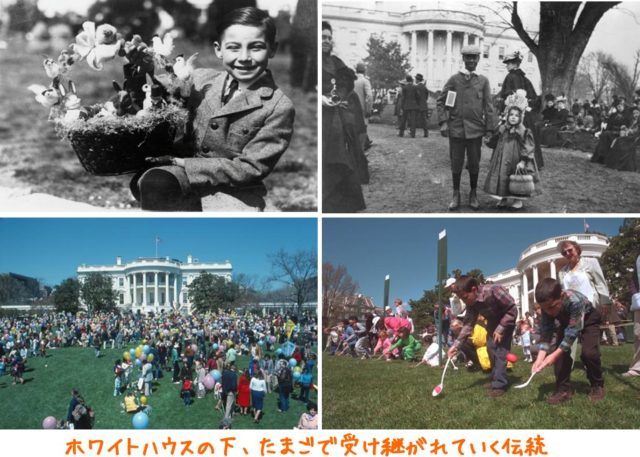こんにちは!たまごのソムリエ・こばやしです。
本日の金曜ロードSHOW!は「ガリバー旅行記」です。地上波初登場ということですが、これ現代風にアレンジされていて、結構面白いです。
さて、このガリバー旅行記の原作「ガリバー小人国へ行く」(スイフト著)は、ほとんどのみなさん絵本でご覧になった事があるかと思います。
船が難破し、流れ着いた王国は小人の国だった。おりしも隣国との戦争中だった小人国にガリバーは協力、敵艦隊の弓矢をメガネで防ぎ船に縄をひっかけて捕まえて帰り、大勝利をもたらした!
・・・・・・絵本だとこういうストーリーです。
では、なぜ隣の国と戦争していたのか?じつはそれは「ゆでたまご」が原因だったんですね。
卵には尖った方と丸い方とがあります。朝食のゆでたまごを『どっちから割るのか』を巡って隣国同士が対立し、戦争を引き起こしているんですねー。
ガリバーの活躍の裏には、たまごが大きく関係しているなんて!意外ですねー。(^^)
以前も当コラムで書きましたが、これは原作執筆当時の英国の宗教対立を面白おかしく批評したもの。原著者のスウィフトさんは、ほのぼの絵本なんてとんでもない、過激な風刺作としてこの本を書いていまして、当時は名前まで偽って執筆していたのだとか。
そう思って今夜放送の映画「ガリバー旅行記」を観ると、また違った感想がでてくるかも!? 個人的に主演のジャックブラックさんは大好きなんですね!ぜひお時間あれば、ゆでたまごの騒ぎを思い出しながら、ぜひごらんになってくださいませ!(映画ではゆで卵は出てきませんが…)