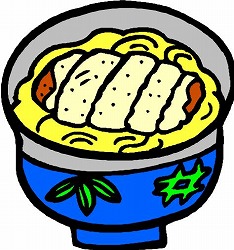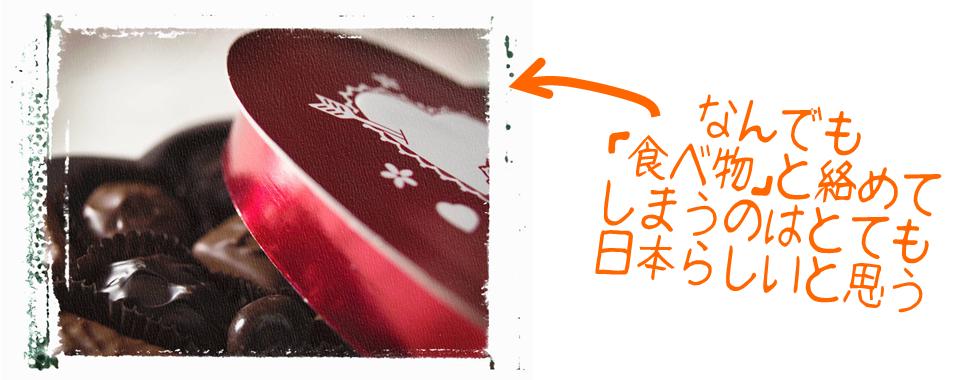
こんにちは。こばやしです。
本日はバレンタインですね。
「女性が男性にチョコを贈る日」というのが日本の習わしで、私も今朝妻からもらってニコニコしています。
が、世界でみると「女性→男性」となっているのは日本と韓国くらいで、
欧米ではキリスト教に由来する成り立ちもあってか、男でも女でも「恋人へ愛の誓いとともに贈り物をする日」となんですね。 「チョコ」という縛りも無く、花やちょっとしたプレゼントにメッセージを添えて贈るのが主流のようです。
反対に、キリスト教が絡んでいることからイスラム圏サウジアラビアでは国を挙げて禁止となっています。 国営放送にて「バレンタインを祝うものには最高で“死刑”もありうる!」なんてコメントも出すくらい・・・!
チョコあげて死刑になるなんて、ビックリですね。
また、“男女どちらからもOK”というのが主流なので、当然ホワイトデーという風習も日本くらいにしか無いわけです。
ちなみに「夏のバレンタイン」ってなんの日か分かります?
中国では「七夕」の日をそう呼ぶそうです。 なるほど、織姫と彦星、言われてみればこれも「男女の愛」がテーマの日ですもんね。
なんにせよ、愛情や感謝を伝え合う日は、多いに越したことはありません。
なかなか普段の日にあらたまって伝えるのって難しいですもんね・・・(^^;)