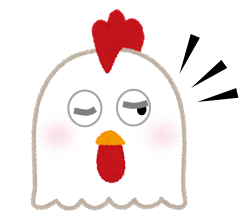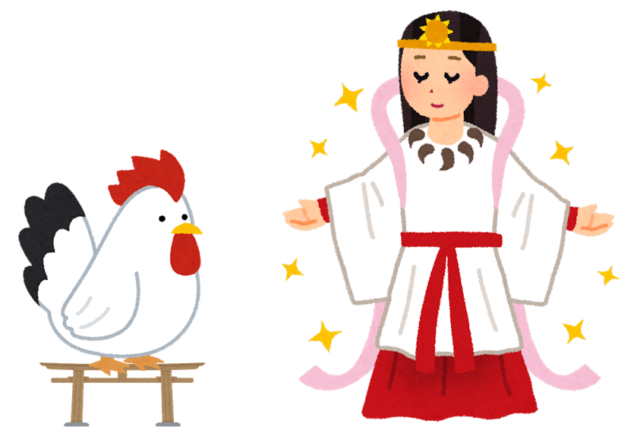こんにちは!
たまごのソムリエ・こばやしです。
南米のアマゾンにすむ
「ツメバケイ」という鳥がいます。

漢字で書くと、
「爪羽鶏」
ハネがツメになったニワトリ。
なかなかカッコいいですね。
ニワトリと同じキジ科ですが、
ぜんぜん別の鳥です。
飛ぶのが苦手で
木から木へ飛び移って移動するそうで、
そこはニワトリと似ているかもしれません。

「卵」の守り方が面白くって、
アマゾン川の真上に伸びた
木の枝に巣を作って卵を産むという
世界最大の河川を使った
かしこい防御システムです。
上記の写真も巣の下はアマゾン川。
たしかに落ちるリスク考えると
外敵も狙いにくいですよね~。
なんで『ツメの羽』なんて
名前がついているかというと、
生れてすぐのヒナの羽に
でっかいツメがついているから。

(ナショナルジオグラフィックより)
飛べないうちはこの2本のツメを
枝にひっかけて移動するんですね。
かっこいい!
ちなみに
羽が生えそろう二週間後になると
ツメは抜けちゃうそうです。
実はのこの爪羽鶏、
ニワトリとは真逆の
面白い生存戦略を摂っているんですね。
それは、
嫌われる
という戦略。
においがすごくって
めっちゃ臭いんです。
糞の匂いをしてまして、
生きていても「腐っている」かのように
誤認させることで外敵に食べられなくする
というすごい作戦です。

匂いに敏感な獣も寄ってこないですし、
もちろん「飼育してペット」なんて
とんでもない匂いですから
人間も捕まえることはありません。
対照的なのがニワトリ。
もともとはアジアの奥地に住む
「セキショクヤケイ」という小さな種でしたが、
好かれる
ことで数が増えていったのです。
正確な朝鳴き
闘鶏としての娯楽性
鳴き声の美しさ
その後は育種がすすみ
肉が美味しい
卵をたくさん産む
・・と、いろんな恩恵を
もたらしてくれるため
人間社会の繁栄と共に数を増やし
現在では世界に230億羽以上のニワトリがいます。
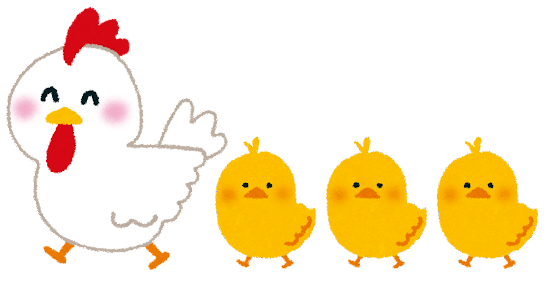
これは栄養の少ない平地に
細々と育つ戦略をとった「イネ」が、ある日
脱粒性(勝手に種が落ちる)を失ったことで
めっちゃ収穫しやすくなり人の手を借りて
世界中で育てられているのと似た構図
ともいえます。
協力者をつくる
相手を近寄らせない
どちらも興味深さを感じますね。
ここまでお読みくださって
ありがとうございます。














 (東京都神社庁
(東京都神社庁